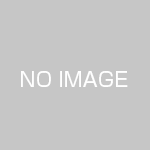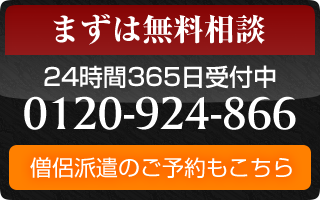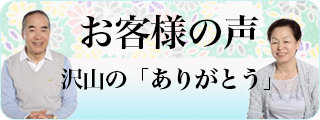四苦とは生(しょう)・老(ろう)・病(びょう)・死(し)、八苦とは愛別離苦(あいべつりく)<愛するものと別れる苦>、怨憎会苦(おんぞうえく)<怨み憎まねばならないものと会う苦>、求不得苦(ぐふとっく)<求めて得られない苦>、五蘊盛苦(ごうんじょうく)<総じて人間の活動による苦>の四苦に先の生老病死の四つを足して八苦。日常生活のなかでもなにげなく使われていそうだが、「この間の試験に四苦八苦したよ」という学生を想像することは最近では難しくなって来たような気がする。
もちろん、「花の命は短くて苦しきことのみ多かりき」という林芙美子の言葉が、しっかりと頭に刷り込まれている昭和の団塊世代以上の方であれば、四苦八苦は日常語であろう。しかし、「花といえば『世界にひとつだけの花』でしょう」と反応する平成の子どもたちには、「苦」は人生にあるはずがないものになりつつある。老人は施設に、病人は病院に送られ子どもたちの目には見えなくなり、死者は遠くの葬儀会場で世間に隠れるようにして消えてゆく。子どもどうしはお互いに傷つかないように距離をとって付き合い、欲しいものは何でも手に入る。生活空間からは「苦」が慎重に排除されている。しかし、それだからこそ、自分の思い通りにならない「いじめ」などの「苦」に遭遇すると、多くの人々が混乱してしまうのではないか。
さらにその子どもたちが老人になるころには、iPS細胞の応用による難病の治療が可能になるだろう。難病に苦しむ方には朗報であろう。しかし、その一方で「老・病」という苦は解消され、「死」という苦も遠い未来に先送りされるということになっているかもしれない。「生む」ということも思い通りになっているかもしれない。四苦八苦のうち少なくとも四苦は、死語になってしまう。しかし、そうなると今度は「自然に老いることができない」や「寿命で死ぬことができない」などと新たな苦が登場する。四苦八苦も新たな意味を携えて復活するのだろうか。
四苦八苦を人間の自然として受容するところに仏教の智慧の歩みは始まる。その智慧を基本にしなければ、文明は苦を排除したつもりが、かえって新たな苦を生みだすだけであろう。