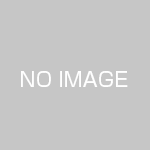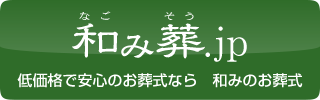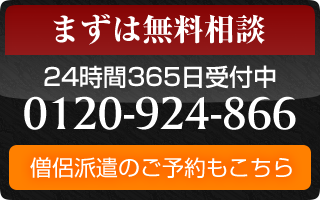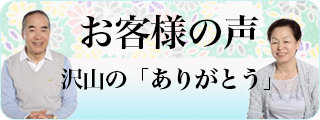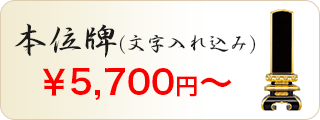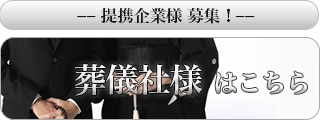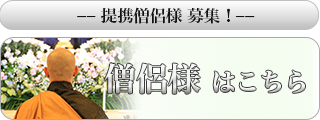元々の戒名というのは2文字で、生前の名前である俗名から一文字、お経から文字を取ってつけるというのが一般的でした。しかし、現代においては戒名の前後に院号や道号、位号などが付帯し、それら全体を戒名と呼んでいます。
「○○院××△△居士」という戒名の例を見てみましょう。まず「○○院」が「院号(印伝号)」であり、その次にある「××」が道号、さらにその後の「△△」が戒名(法名・法号)、最後の「居士(大姉・信士・信女など)」が「位号」と呼ばれるものです。
通常、戒名といえばこの全体を意味しますが、元々の戒名は位号の前にある漢字2文字のみであり、その他は社会的な地位や財力を表す修飾文字になります。つまり、文化的な都合で付加されるようになったものなのです。